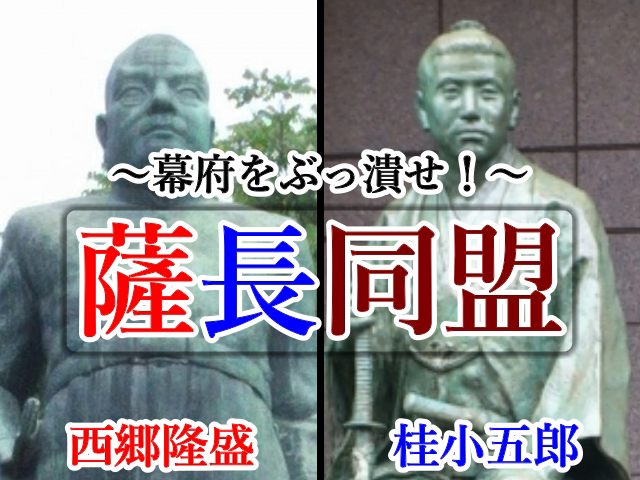
倒幕運動始動。
再び長州藩内に尊王攘夷を返り咲かせた高杉晋作だが、以前の尊王攘夷とは少し違っていた。
定説では、天皇を尊ぶことを尊王、外国を打ち払うことを攘夷という。
下関戦争で異国の強さを思い知った高杉は、
「いまの長州、そして日本では到底太刀打ちできない。異国の技術を吸収した後に、堂々と渡り合おう。」
それこそが誠の攘夷であると考えた。
また、
「俺たちを京から追い出したり、攻撃吹っかけてきやがってこのクソ幕府。お前らは俺たちが嫌いだが、俺らもお前らがもっと嫌いになった。もう従いませんよ徳川さん!」
実際はそんなことは言っていないとは思うが、長州征討を機に倒幕路線を進めていったのは間違いない。
長州藩は幕府に対抗するため下関戦争で敵国であったイギリスから銃器や艦船を購入し、軍備拡大をしていった。
これを知った幕府は、
「いや、長州はなにしとるんや。俺たちに歯向かうつもりか。」
長州藩に対して、十万石の削封や長州藩主毛利敬親の隠居などの処分を命じる。
※削封とは武士の所領や城・屋敷の一部を削減することである。
しかし、長州藩はこの通達に応じない。すでに藩内では倒幕の志が高いものになっていた。
これを受けて幕府は、長州に再度兵を出すことに決める。
「今度こそ、徹底的にこらしめてやる」
幕府もフランスの援助のもと軍備拡大をしていきました。
幕府はもともと、井伊直弼(開国派)が政権を握っていた時から、異国との関わりが多かった。特にフランスは幕府との結びつきが強く、横須賀製鉄所の建設や横浜仏語伝習所を作り、そこで幕臣を教育したりと、さまざまな支援をしていた。
面白いものである。
数年前まで、あれだけ「攘夷だ」「異人をぶった斬ろう」などと言っていたのに、内乱をするためにも異国の力が必要になっているのだから。
下関戦争で長州藩が異国にやられ、西洋兵器の力を知る。
ただ、西洋の力を知ったのは、長州だけではない。
これを機に多くの者が開国を意識していったと思う。
あの「藩」も幕府に見切りをつける
幕府が第一長州征討で勝利し、自信過剰になっていたのを見て、不信に思っていた藩がある。
そう、薩摩藩である。
八月十八日の政変、禁門の変と、長州をやっつけるために協力していた会津藩とも合わなくなり、薩会同盟を勝手に破棄。
「これからは幕府ではなく、雄藩が天皇をお支えするのだ」
まだ完全に幕府の敵になったわけではないが、「公武合体」で一時堅かった両者の関係は徐々に弱まっていく。
元治2年(1865年)2月。
幕府は天狗党(水戸藩過激攘夷派)の大量斬首を行う。
以前にも安政の大獄により攘夷派が弾圧されたが、今回の処分は幕府の攻撃により降伏した天狗党員の823人のうち352人を斬首といった桁違いの弾圧である。また、処刑は天狗党員の親族にも及び、多くの血が流れた。
西郷と同じく薩摩藩士の大久保利通は日記に「聞くに堪えない。このむごい行為は幕府滅亡を自ら示したも同じ。」と記した。
西郷や大久保ら薩摩藩はこの仁義なき処分に怒り、幕府に対して決定的に失望したのである。
薩摩藩は「幕府を倒すにしても雄藩の力が必要だ。俺たちと手を取って幕府をやっつけるそんな肝が据わった藩はいるだろうか」と考えた。
思い当たる藩は1つしかない。
長州藩である。
すでに幕府を見限っているという点で倒幕路線の先輩である。有能な人材もたくさんいる。幕府を倒すには長州藩ほどふさわしい藩はいない。
ただ、難しい。。。
八月十八日の政変、禁門の変を経て、長州の薩摩に対する憎しみは大きいものとなっている。そんな相手が自分たちと手を組むはずがない。
もう幕府の味方はしたくない。けれど今はそれができる状態ではない。
実質、薩摩藩も長州藩と同じ孤立状態だった。
「幕末のヒーロー」ここで登場

幕府ではなく雄藩による新政府を作ることこそが異国に対抗できる最善の方法だ、と考えていたのは薩摩藩、長州藩のものだけではない。
土佐脱藩中岡慎太郎もその一人だった。
中岡は土佐を脱藩して長州の尊王攘夷過激派グループ(久坂玄瑞と一緒)に加入し、禁門の変でも長州側に立って一緒に戦った。この禁門の変での敗北から長州一藩では倒幕は不可能と知り、雄藩連合によるものでなければならないと考えていた。
同じく土佐脱藩の坂本龍馬も師匠である勝海舟から雄藩連合による新しい日本を造ることの重要性を教えられていた。
「新しい日本を造るために長州は要になる。それともう一つは、、、」
「第一次長州征討の際、征討軍の参謀西郷隆盛は戦を好まず、長州に対して家老の処刑で済ます処分を命じた」
「佐幕派の会津藩との密約薩会同盟をすでに破棄」
中岡と龍馬は、こういった薩摩藩のかすかな変化を感じとり、
「薩摩も幕府との関係は冷え切っているのではないか」と考えた。
長州と薩摩が手を結ぶことによって幕府に対抗できる力が生まれる。
では、
どうすれば、憎み合う関係の両藩をくっつけることができるのか。
この頃、龍馬は長崎で貿易会社を作り、イギリスなどと取引をしていた。亀山社中(後の海援隊)である。
龍馬は亀山社中を通してビジネスを経験する。
「お互い嫌いな関係でも、互いに利益を出せればいい。」
「薩摩藩が長州藩にやりそうもないもの。でも長州藩が欲しいものを渡す。」
「長州藩が薩摩藩にやりそうもないもの。でも薩摩藩が欲しいものを渡す。」
龍馬はビジネスで両藩連携のお膳立てをしようと考えた。
長州藩は軍備拡大のため武器が欲しい。しかし、禁門の変を経て「朝敵」となった長州は幕府から武器の購入を禁じられている。
薩摩藩は米が欲しい。薩摩はイギリスの支援のもと軍備拡大をしていたが、拡大に伴い兵を養う兵糧米も必要となる。また薩摩は火山の噴火、台風といった災害も発生しやすく農業生産に長けた藩とは言えない。
龍馬はこの両藩の欲しいものを取引することによって、和解させようと考えた。
イギリスの武器商人グラバーから武器を薩摩名義で購入し、それを長州に売る。長州は代わりに米を薩摩に売る。
龍馬率いる亀山社中の仲介のもと、渡しそうもないものをお互い渡し、長州と薩摩の和解は成功したのである。
この和解があって、慶応2年(1866年)1月21日。薩摩藩西郷隆盛と長州藩桂小五郎は龍馬仲介のもと同盟を結ぶ。
これが薩長同盟である。公の取り決めではなく密約であったため「薩長密約」とも呼ばれる。
簡潔にこの同盟の内容を言うと、
長州藩が幕府と戦になったならば、長州が優勢となっても劣勢となっても薩摩はこれを支援する。場合によっては幕府、佐幕派の会津藩、桑名藩とも戦う
というものである。
これは、単なる友情同盟ではなく、倒幕を見据えた軍事的な同盟である。
幕府は
薩摩が長州に手を貸すなどありえないことだと思っていただろうし、
ましてや
両藩が自分たちを追いやるための同盟を結んでいるなんて想像もしていなかっただろう。
・今回のポイント
坂本龍馬、中岡慎太郎らの活躍により、
犬猿の仲である長州と薩摩の和解が成功。
大政奉還に向けた佳境に入る。
↓
薩長同盟。
