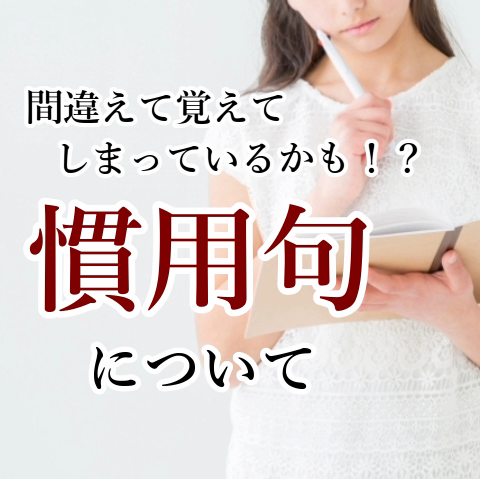
「慣用句」とは
慣用句は二つ以上の単語が結合して、全体が特定の意味を表わす言いまわしのことです。「常套句」「常套表現」「イディオム」とも呼びます。
慣用句は読者や視聴者に印象づけるために新聞記事やテレビのニュースなどでよく使われています。
私たちも普段生活している中でたくさんの慣用句を目にしたり耳にしたりする機会があると思いますが、間違えて覚えてしまっている表現もあるかもしれません。
例えば、「今回のこの企画は汚名を挽回するチャンスだ」
正しくは「汚名を雪ぐ」で、「挽回する」は間違いです。
「挽回するってよく耳にするから、正しい表現だと思っていました」
そう思っていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私も最近まで「挽回する」が正しいと思っていました。
今回は、「正しい感じがするだけで、実は正しくない」
そんな慣用句を紹介していきます。
怒り、心頭に~
怒り、心頭に達する ✖
怒り、心頭に発する 〇
意味:心底から激しく怒る
「心頭」とは心、心の中という意味です。
「心まで怒りという感情が浸透しています」
ということから「達する」を使いたい気持ちも分かりますが、間違い。
まず、心中に怒りが生じるということで「怒り、心頭に発する」が正しいです。
文化庁が発表した平成24年度「国語に関する世論調査」では、本来の言い方とされる「怒り心頭に発する」を使う人が23.6%、本来の言い方ではない「怒り心頭に達する」を使う人が67.1%という結果がでています。
汚名を~
汚名を挽回する ✖
汚名を雪ぐ 〇
意味:不名誉な評判や悪評を振り払うこと
「挽回する」は失ったものをとりかえすこと。「汚名を挽回する」では汚名を取り戻すという本来とは真逆の意味になってしまう。ここは、「汚名・恥などのつぐないをする。恨みをはらす。」といった意味を持つ「雪(すす)ぐ」が適切です。
平成16年度「国語に関する世論調査」では、本来の言い方とされる「汚名返上」を使う人が38.3%、本来の言い方ではない「汚名挽回」を使う人が44.1%という結果がでています。
歓心を~
歓心を呼ぶ、集める ✖
歓心を買う 〇
意味:人の気に入られるようにつとめる。
同音異義語に要注意。感心なら「呼ぶ」、関心なら「集める」。そして「歓心」なら「買う」。歓心は人の心をよろこばせることです。
ちなみに、感心はすぐれたものとして、深く感じて心を動かされること。関心は物事に興味をもったり、注意を払ったりすること。
※大辞林第三版より引用
窮地に~
窮地に陥る ✖
窮地に立つ 〇
意味:追い詰められて逃げ場のない苦しい状態や立ち場にいる。
「窮地」とは逃れようのない苦しい立場のこと。「陥(おちい)る」は落ちて中に入るという意味なので、ここでは「立つ」が適切です。また、窮地から脱出する、逃れるという意味で「窮地を脱する」もよく使われます。
苦汁を~
苦汁を味わう、飲む ✖
苦汁を嘗める 〇
意味:つらくて嫌な思いをする。
「苦汁」とは名前からも分かる通り苦い汁のこと。転じて苦い経験という意味を持ちます。好ましいものではなく、「味わう」「飲む」などそんな余裕もありません。
「苦さを実感する」という意味で、ここは「嘗(な)める」が適切です。
小耳に~
小耳に入れる、聞く ✖
小耳にはさむ 〇
意味:ちらりと聞く。
ここでの「小耳」とは部位のことではなく、「ちらりと聞く。ちょっと耳にする。」という意味。
失笑を~
失笑を浴びる ✖
失笑を買う 〇
意味:愚かな言動で、他の人から笑われる。
失笑とはおかしさをこらえることができず吹き出すこと。自分ではそうなるとはまるで気づかず、わざわざお金を出して「買う」ように、思いがけず相手から「失笑」という反応を返されるという意味で「失笑を買う」。
また、「失笑する」という言葉の意味について、平成23年度「国語に関する世論調査」では、本来の意味である「こらえ切れず吹き出して笑う」を選んだ人が27.7%、本来の意味ではない「笑いも出ないくらいあきれる」を選んだ人が60.4%という結果がでています。
取り付く~がない
取り付く暇がない ✖
取り付く島がない 〇
意味:相手がつっけんどんで話を進めるきっかけがみつからない。
ここでの「島」の意味は手がかり、助けとなる物事。頼りとしてすがるところがないという意味で「取り付く島がない」
~覚めが悪い
目覚めが悪い ✖
寝覚めが悪い 〇
意味:過去にした悪い行為が思い出されて、良心がとがめる。
朝、起きるのが苦手な人は「目覚めが悪い」を使ってもいいと思います。
「寝覚めが悪い」は眠りから覚めたときの気分がよくないこと。転じて「あと味がよくない」「良心がとがめる」ことを意味します。
平成27年度「国語に関する世論調査」では、本来の言い方とされる「寝覚めが悪い」を使う人が37.1%、本来の言い方ではない「目覚めが悪い」を使う人が57.9%という結果がでています。
見栄を~る
見栄を切る ✖
見栄を張る 〇
意味:自分をよく見せようとして外見を飾る。
「見栄(みえ)」は見た目、外見のこと。「見栄を張る」はうわべを飾ることです。
同音異義語で「見得」もあります。歌舞伎の決めのポーズのことで、こちらは「見得を切る」が適切で、おおげさな言葉や態度で、他人に自信のほどを示すという意味になります。
最後に
みなさん、どうだったでしょうか。
間違えて覚えてしまっていた表現はありましたか。
慣用句は今日述べた以外にもたくさんありますし、まだ曖昧に覚えてしまっている表現もあると思います。私もそうです。
慣用句は日本語独特の表現。こういった機会に見つめなおすのも面白いですね。
ご覧いただきありがとうございました!
